ただ乗っているだけで「上手くなった」ような錯覚すらあるミニベロ
あなたは「Tyrell」と言うブランドを聞いたことがありますか?
オープン以来、様々なミニベロを見てきた「自転車処ぽたりんぐぅ」店長が太鼓判を押すミニベロブランド。
今回は入門モデル「Tyrell FXα」を納車させていただいたので
ミニベロってどんな特徴がある自転車?
タイレルのどこがすごいの?
そんな疑問を
大阪府堺市のJR阪和線「堺市」駅前の
ミニベロやカスタムが得意な
ポタリング(自転車散歩)プロショップ
「自転車処ぽたりんぐぅ」が
12年以上のポタリングPROショップ経験と
大小1000件以上のカスタム経験の中から詳しくお伝えしていきます。
香川県発のミニベロブランド「Tyrell」

「Tyrell(タイレル)」は香川県発の日本のミニベロブランドです!
創業者で社長の廣瀬さんが自宅ガレージからスタートさせたという、こだわりのつまったブランドです。
規模の大きい小さいでどちらが正解と言うのは不毛な話ですのでここではしませんが。
自分の理想を目いっぱい詰め込んで自転車を作りたいとなると小規模な方が有利になることも多いです。
個人的にはこういう独自のコンセプトが詰まったメーカーはとても信頼できると思っています。
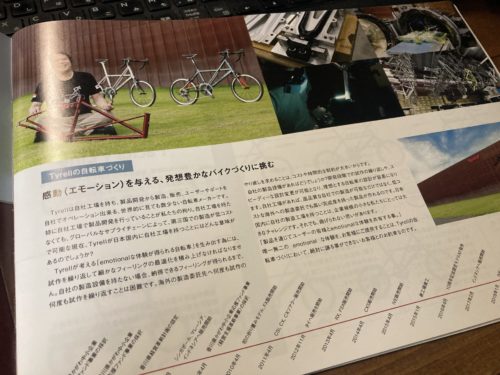
それぞれの自転車メーカーで目指すところはそれぞれです。
タイレルの場合は、自転車によるエモーショナル(感動的)な体験をユーザーの皆さんに共有して欲しいとの
ひとつのコンセプトを提案しつづけています。
新しい自社工場で自分たちの手で設計、テスト、修正を繰り返し納得いく製品づくりを目指している精力的なブランドです。
自転車に正解はないと思いますが、「Tyrell(タイレル)」ブランドの目指すミニベロ(一部ロードバイクも)を追及する自転車メーカーです。
そもそも「ミニベロ」って?
そもそもミニベロってなに?
っていう人は最近は少ないですかね。

mini(小さい・英)+velo(自転車・仏)の造語です。
なぜ peti-velo にしなかった?と言うツッコミはおいておいてww
一般的には20インチ以下の小径自転車をさすことが多いようですが定義はあいまいです。
最近の自転車用語はクロスバイクにしろ定義があいまいにされているものも多いので問題ないと思います。
この「ゆるさ」が自転車の魅力のような気がします。
話がそれました・・・
自転車と言う乗り物は適材適所で利用してこそ、その機能が十分に発揮できる乗り物です。
ミニベロの特徴、メリット、デメリットと、ミニベロに適したシチュエーションなどをお話しします!
但しメリットとデメリットは表裏一体の部分がありますので使用用途によって大きく変わってしまいます。
ミニベロのメリット
メリット1:加速性
タイヤが小さいと「こぎ出しに必要な力」が小さくて済みます。
ゼロから発信するときにどれぐらいの力が必要かと言うことですね。
この性格はホイルの半径に起因してくる物理的な特徴ですのでミニベロ特有のものと言えるかもしれません。
詳しくは下のリンクから関連記事へどうぞ!

メリット2:旋回性
いわゆる「小回りがきく」と言うことです。
これはキャスター角やトレール角と言う設計要素に起因してくる性格です。
曲がるということは、究極的にはバランスを意図的に崩していることですのでバランスの崩れに対して繊細とも言えます。
裏返すと直進安定性は低く、ライダーの挙動に反応しやすいです。
クイックなアクションの連続のBMXレースなどはイメージしやすいかも。
メリット3:トルク伝達の効率がいい
これも先ほどの加速度と似た効果ですが、「小さい力で動かすことができる」と言うことです。
止まってるタイヤをゼロから動かすときは、タイヤが小さいほど必要な力は少なくて済むという感じです。
この特徴が顕著なのが「坂道」です。
スピード競技をするのでないならばミニベロは基本的には坂道が得意です。(ポジションの話などもありますが・・・)
メリット4:気楽さ
いきなり感覚的になりましたが、気分的に楽ですw
ロードバイクほどスピードも出ませんし、長距離ライドは苦手になりますが堅苦しさはなくなります。
街中を散策したり、普段着で気楽に乗ったりと日常の生活に近い環境でスポーツバイクを楽しめます。

ミニベロのデメリット
ミニベロはメリットとデメリットがそれぞれ、際立っている乗り物です。
メリットも多い分、裏返しのデメリットも増えていきます。
「クセがつよい」と言うような評価を受けやすいのはそのせいですね。
デメリット1:巡航性能
これは走りの「伸び」です。
走行中、足を止めて「サーッ」と惰性で進んでいく感覚の事だと思ってください。
実はメリット1の加速性の裏返しですがタイヤ半径が小さいと働く慣性力が弱まり惰性での伸びが期待できなくなります。
ミニベロがロングライドが苦手と言われる理由の一つがこちらですね。
理屈っぽいのが好きな方は是非関連リンクも読んでみてくださいね。

デメリット2:剛性が低い
これは「自転車のガッチリ感」のようなものです。
自転車は乗っているあなたが想像している以上に「しなって」います。
特にフレームの剛性感はそのまま自転車の正確に反映されてしまいますので影響が大きいです。
原因は
「フレームの構成パイプが長くなる」のと
「前三角形が崩れやすい」
と言うことです。
これを言い出すと長くなるのでまたどこかで解説します。
デメリット3:重量アップ
ミニベロの方が軽量と勘違いされる方が多いですが意外と逆のことが多いです。
冷静に考えてもらえばわかると思いますが、タイヤが小さい分フレームの構成材(パイプ・チューブ)は長くなります。
と言うことは使う金属や構造材が多く必要になり重くなるのです。
デメリット4:不安定感
ミニベロに乗ると「ふらつて怖い。」と感じる人が少なくありません。
これはメリット2:旋回性の裏返しの要素が大きいのですが結構複合的なことも多いです。
ミニベロは設計上の制約が想像以上に多く、ホイルベースやヘッド角度、BBハイトなど安定性に関する要素が
反対に作用することが多いため、慣れない方は「不安定感」を感じるわけです。
ミニベロに適したシチュエーションは?
こうやって見ているとミニベロが得意なところ、不得意なところがぼんやり見えてきますね。
自転車処ぽたりんぐぅが考えるミニベロの活躍するシチュエーションは
- 信号や曲がり角による、ストップ アンド ゴーの多い街中
- 中距離(個人の主観でOK)程度のサイクリング
- スピードを求めないアップダウンの多いコース
と言った感じです。
ミニベロと言っても範囲が広いので、それぞれの自転車が活躍できる場面を考えてあげればいいですね!!
高性能入門モデル 「Tyrell FXα」

「Tyrell(タイレル)」を代表する折りたたみモデルのラインナップ「FX」シリーズの入門編的位置づけの「FXα」です。
仕様をパッケージ化し、コンポーネント、塗装などを見直して比較的お求めやすい価格設定を目指したモデルです。
ただし、かなり高性能でポイントを押さえているので一般的なミニベロに比べると高く感じてしまうかもしれませんね。

フレームの構造は上位モデルの「FX」と同じものです。
十分に長く設定されたリアセンターはミニベロの弱点を補強してくれます。

標準コンポーネントは「SHIMANO SORA」フロントシングルの1x9Speedです。
街乗りや、気楽なポタリングなら十分すぎる性能です。
ホイルは11s対応ですのでカスタムベースで選んでくださる方も多いですね。
ディーラーによるカスタムの場合はメーカー保証が継続されるのもうれしいですね!!!

上位モデルの塗装はパウダーコーティングで有名な「カドワキコーティング」製ですが、FXαでは不採用。
確かにカドワキ製の塗装は素晴らしい仕上がりですがFXαも標準的な自転車の塗装と比べれば劣るものではないですから
ここは、それぞれのオーナーさんのこだわりどころでしょうね。

折りたたみも従来の「FX」シリーズと同様。
折りたたみ時の寸法は正直少し大きめです。電車の車内や駅構内の移動では少し気を使わないといけないかなと言うレベル。
但し、輪行時の駅などでの移動は割合としては大きくないので際立って不具合を感じるほどではないでしょう。
※都市部のターミナル駅などでは結構移動させられたりしますので注意が必要です。
トップチューブ部分にヒンジ(折りたたみの可動部)を配置しない設計になっています。
ミニベロにありがちな剛性感の不足を防ぐフレームと折りたたみ方法のデザインになっています。
主観で語ります! ミニベロとしての「Tyrell」

実は、「自転車処ぽたりんぐぅ」をオープンするまえから一般向けの展示会などでは「Tyrell(タイレル)」を見て一目ぼれでした。
オープン一年目は一般車・ママチャリ中心に営業していたのですが
軌道に乗り出したころに取引のお願いに香川県さぬき市へ直行してました。
「自転車処ぽたりんぐぅ」もミニベロが得意とおっしゃっていただけるので、ミニベロ屋目線で「Tyrell(タイレル)」のいいところを語ります。
ミニベロの長所を活かし、短所を克服するデザイン
前項でもお話ししたようにミニベロは長所・短所の振れ幅が大きい自転車です。
目的にマッチした人はとことん気に入ってくれますし、
イメージと違った人は全く気に入ってもらえませんw
まさに「Tyrell(タイレル)」は長所を最大限に活かし、短所を克服することでミニベロのポテンシャルを飛躍的に向上させた自転車になってます。
・フレームデザイン
ミニベロの構造的な課題として「直進安定性」、「剛性の確保」があります。
タイヤの小ささゆえに非常に両立させるのは難しい要素ですがフレームデザインでそれを克服しているのが「Tyrell(タイレル)」の一つの特徴です。
一般的なロードバイクよりも長いホイルベースと構造的に強固な三角形を組み合わせたスラントデザインのフレームは「Tyrell(タイレル)」の代名詞的です。
あとで触れますが、フレームとは逆に剛性感の高いミニベロホイルと相まって、非常にキビキビ反応してくれるフレームが仕上がっています。
・折りたたみ機構
「Tyrell FX」から折りたたみモデルの展開が開始されましたが、オーナーさんたちが一番驚いたのはミニベロらしからぬ走行性能でした。
前項でも書いたフレームデザインに加えて、何度もテストを重ねて納得いくまで開発された折りたたみ機構は今現在でも他メーカーではマネができていないと思います。
トップチューブにあたるフレームの前半分に折り畳み構造を配置しないことでねじれに対する剛性が格段に上がります。
・高性能ホイール
「Tyrell(タイレル)」の特徴は独自で開発したホイルにもあります。
ミニベロのホイルに求められる要素は
- 回転性能の高いハブ
- 適度に重量配分されたリム(タイヤ含む)
であると「ぽたりんぐぅ」では考えています。
Tyrellのホイルは非常にそのあたりのバランスが良いホイルに仕上がっています。
ホイルの重量的な偏芯を解消してやるホイルバランスをとってやるとミニベロとは思えない走りを見せてくれます。
・重量感
ロードバイクをはじめ、スポーツバイク全体的に「軽さは正義」と言った風潮があります。
フルサイズバイクにとってはある意味正論なんですがミニベロにとっては少し違うと考えています。
軽くなると具体的に何が良くなるかと言うと、単純に自転車を動かすエネルギーが小さくなるほかに
ライダーの挙動が反応よく自転車に伝わる。
と言う強みがあります。いわゆる反応がクイックになる、キビキビ動くというようなフィーリングです。
しかし、そもそもが反応性のいいミニベロでさらにクイックさを求めていくとどうなるか?
反応が良くなり、自動車などでいうところの「ピーキー」な状態になります。
要するに、反応がシビアすぎて自転車経験の豊富な方にはそれでいいかもしれませんが、
自転車歴が浅かったり、そもそもレーシーなものを求めていないユーザーさんにとっては逆効果になります。
適度な重量は「安定感」や「まろやかなフィーリング」にもつながる重要な要素です。
「軽さ」を一つの側面からしか見ないことは自転車の性格の判断を見誤るので注意が必要と考えています。
しっかり走ってくれるミニベロ
自転車処ぽたりんぐぅでは常々
「自転車を主役にしない、自転車を最高の脇役にすることで自転車ライフは充実する。」
と考えています。
しかし、気持ちよく走ってくれる自転車は絶対条件です。
当店で多いのが、
「ロードバイクからの乗り換え」
のご相談です。
ロードの走行感やフィーリングになれてしまったオーナさんでは従来のミニベロではイメージのギャップが大きくなります。
これはミニベロが悪いというよりは両者のベクトルが大きく離れてしまっているからです。
「Tyrell(タイレル)」はリジッドモデル(折りたたまない)もフォールディングモデル(折りたたみ)も
それぞれがミニベロの良さを残しつつ、ロードバイクになれた目の肥えたオーナーさんも満足してくれる走りを実現します。
この両立を達成しているミニベロは実は少ないのが現実です。
まとめ。走行性能よりでカバー範囲の広い万能ミニベロ。
ミニベロに限らず、自転車は「向き・不向き」です。
走行性能や、折りたたみ機能の有無、趣味性、価格、などいろんな要素を含めて折り合いの取れるところを選ぶのが
上手な自転車選びだと自転車処ぽたりんぐぅでは考えます。
ロードバイクでロングライドを楽しんでいた方で、少しゆっくり目の自転車ライフに切り替えたい方や
折りたためて、そのうえしっかり走れる輪行旅をしたいような方には
「Tyrell(タイレル)」は非常に「向いている」選択肢になるかもしれませんよ!
試乗車のご用意もありますのでご興味を持っていただいた方は是非お問い合わせくださいね!
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
ブログ記事のシェア、ブログのフォローもお願いします!!
励みになります!
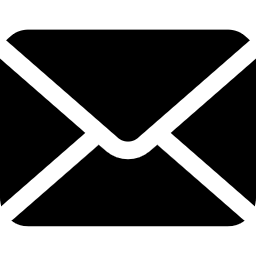


コメント